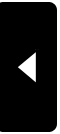2020年08月24日
飯盒飯の炊き方
飯盒飯の炊き方にコメントを頂きましたので、もう少し詳しく書いてみます。
この炊き方は昔、飯盒で焦がしてばかりで、お米屋さんに聞いて教わりました。強火を使用しませんので飯盒を焦がす心配もだいぶ減りました。
また、炊き方に関わらず、水とお米の分量は大切ですが、多少の分量のずれも失敗無く炊ける率が高いです。
ただし、下準備としてお米をしっかり洗うこと、お米と同じ分量の水を入れて1時間ほど水に浸けておくのは必須です。気温が低いときには長時間浸けておいた方が失敗しません。
私の飯盒はいわゆる兵式と呼ばれる物で昔からあるものです。最近は丸形のものやメスティンと呼ばれる長方形の物も飯盒の一種として扱われていますが、私にとっては兵式がやっぱり飯盒と呼べる唯一の炊飯器です。

さて、この飯盒、アルミ製です。温まりやすいですが、あっと言う間に冷めます。ごはん炊きには実は不向きです。
また、飯盒は熱のまわりがバーナーであぶっている部分に偏ります。飯盒の中心ばかり柔らかく、周りは硬いなどとムラが出来る場合があります。
そこでふたをしないで、弱火で炊き始めます。ぐつぐつなってきたら、たまにへらやスプーンで優しくかき混ぜてむらにならないようにします。水に浸けたお米は大変欠けやすいので、やさしくかき混ぜます。この時の火の強さで、出来上がりのお米の硬さを調整します。火を強く早く水気を無くせば、出来上がりは硬めになります。
ふたをしていませんので、水気はだんだん無くなってきます。水気が減りお粥状になり優しくかき混ぜるのが難しくなってきたらふたをし、可能な限りとろ火にします。とろ火ですので吹きこぼれることはありませんので、ふたの上に重しを置く必要はありません。火が消えたら、アルミはあっと言う間に熱を失い失敗しますので、火が消えないように注意が必要です。特に外で調理する場合は風防などで消えてしまうのを防いでください。
とろ火で25分から30分ほど調理したら出来上がりです。絶対にふたを取ってはいけません。
とろ火調理の時間の長さでお焦げの具合を調節します。私の飯盒とストーブの場合ですと25分ほどでだいたいうっすらお焦げになります。
とろ火調理が終わったらしゃり切りをします。お寿司屋さんがお酢を混ぜてかき回しながら冷ますのをしゃり切りと呼びますが、あれと同じ要領で、ふたを取ったらお米をまんべんなくかき回して余分な水分とあら熱を取ります。かき混ぜ終わったら、ふたを少しあけた状態で閉めて、5〜10分待ったら出来上がりです。
飯盒とストーブの違いで多少調理時間が変わるかもしれませんが、だいたいの目安です。南部鉄器の釜で炊いたこともありますが、同じ方法で炊けます。ただし、熱持ちがいいので、とろ火調理の時間は短めにするのがこつです。
機会がありましたら、是非お試しください。お米をかき混ぜるときは優しく、とろ火調理中は熱が逃げてしまいますので決してふたをあけてはいけません。
この炊き方は昔、飯盒で焦がしてばかりで、お米屋さんに聞いて教わりました。強火を使用しませんので飯盒を焦がす心配もだいぶ減りました。
また、炊き方に関わらず、水とお米の分量は大切ですが、多少の分量のずれも失敗無く炊ける率が高いです。
ただし、下準備としてお米をしっかり洗うこと、お米と同じ分量の水を入れて1時間ほど水に浸けておくのは必須です。気温が低いときには長時間浸けておいた方が失敗しません。
私の飯盒はいわゆる兵式と呼ばれる物で昔からあるものです。最近は丸形のものやメスティンと呼ばれる長方形の物も飯盒の一種として扱われていますが、私にとっては兵式がやっぱり飯盒と呼べる唯一の炊飯器です。

さて、この飯盒、アルミ製です。温まりやすいですが、あっと言う間に冷めます。ごはん炊きには実は不向きです。
また、飯盒は熱のまわりがバーナーであぶっている部分に偏ります。飯盒の中心ばかり柔らかく、周りは硬いなどとムラが出来る場合があります。
そこでふたをしないで、弱火で炊き始めます。ぐつぐつなってきたら、たまにへらやスプーンで優しくかき混ぜてむらにならないようにします。水に浸けたお米は大変欠けやすいので、やさしくかき混ぜます。この時の火の強さで、出来上がりのお米の硬さを調整します。火を強く早く水気を無くせば、出来上がりは硬めになります。
ふたをしていませんので、水気はだんだん無くなってきます。水気が減りお粥状になり優しくかき混ぜるのが難しくなってきたらふたをし、可能な限りとろ火にします。とろ火ですので吹きこぼれることはありませんので、ふたの上に重しを置く必要はありません。火が消えたら、アルミはあっと言う間に熱を失い失敗しますので、火が消えないように注意が必要です。特に外で調理する場合は風防などで消えてしまうのを防いでください。
とろ火で25分から30分ほど調理したら出来上がりです。絶対にふたを取ってはいけません。
とろ火調理の時間の長さでお焦げの具合を調節します。私の飯盒とストーブの場合ですと25分ほどでだいたいうっすらお焦げになります。
とろ火調理が終わったらしゃり切りをします。お寿司屋さんがお酢を混ぜてかき回しながら冷ますのをしゃり切りと呼びますが、あれと同じ要領で、ふたを取ったらお米をまんべんなくかき回して余分な水分とあら熱を取ります。かき混ぜ終わったら、ふたを少しあけた状態で閉めて、5〜10分待ったら出来上がりです。
飯盒とストーブの違いで多少調理時間が変わるかもしれませんが、だいたいの目安です。南部鉄器の釜で炊いたこともありますが、同じ方法で炊けます。ただし、熱持ちがいいので、とろ火調理の時間は短めにするのがこつです。
機会がありましたら、是非お試しください。お米をかき混ぜるときは優しく、とろ火調理中は熱が逃げてしまいますので決してふたをあけてはいけません。
ワクチン接種終えました。キャンプも楽しんでいます。
またまた Bear Brook State Park でキャンプ
自作ローテーブル用ウィンドスクリーン製作
2021年初キャンプ(長いです)
ローテーブル作成
明日から、2021年初キャンプ
またまた Bear Brook State Park でキャンプ
自作ローテーブル用ウィンドスクリーン製作
2021年初キャンプ(長いです)
ローテーブル作成
明日から、2021年初キャンプ
この記事へのコメント
こんばんは!
早速ありがとうございます(^ω^)
私もご飯は飯盒派!
まったくこの感じのものを使っています。
最近は焚き火で炊くことが多いので、たまにバーナーでやると焦がしたりします(笑)
とても分かりやすいご説明だったので、私も次回試してみようと思います!!
早速ありがとうございます(^ω^)
私もご飯は飯盒派!
まったくこの感じのものを使っています。
最近は焚き火で炊くことが多いので、たまにバーナーでやると焦がしたりします(笑)
とても分かりやすいご説明だったので、私も次回試してみようと思います!!
Posted by オディール at 2020年08月24日 18:47
at 2020年08月24日 18:47
 at 2020年08月24日 18:47
at 2020年08月24日 18:47オディールさん
飯盒飯を焚き火で炊くとはすでに上級者ではないですか!
私はいつも放置して焦がすので焚火調理は苦手です。
この炊き方とろ火を使いますので焚き火は難しいですが、ぜひお試しください。
飯盒飯を焚き火で炊くとはすでに上級者ではないですか!
私はいつも放置して焦がすので焚火調理は苦手です。
この炊き方とろ火を使いますので焚き火は難しいですが、ぜひお試しください。
Posted by 吉田河馬歯 at 2020年08月26日 23:09
at 2020年08月26日 23:09
 at 2020年08月26日 23:09
at 2020年08月26日 23:09